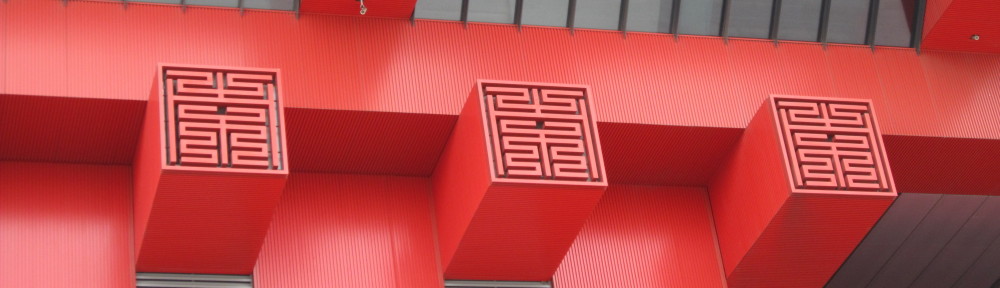野田 英二郎
1.はじめに
ただ今、同学の宮崎さんからご懇篤な紹介をいただいた野田でございます。本日は、こちらの「九条の会」にお招き頂き、恐縮しております。外務省という役所につとめていましたが、退職してからもう20年以上になります。本日お話しする内容も全くの個人的見解です。
「日中関係所感」という表題でおはなしさせていただくことになっております。日本にとりまして、中国との関係は、有史以来の日本の対外関係のなかで、圧倒的に大きな部分を占めています。しかし、教室でお借りしたこの地図が示すとおり、日本は小さな島国で、アジア大陸から離れています。地続きで国境を接し、となりの国を肌身で感ずるということが全くできません。ですから、われわれ日本人にとっては、中国を中心とするアジア大陸のことは、理解が容易でありません。海のむこうのことはわかりにくいので、ひとりよがりになりがちです。われわれ日本人としては、島国の者として、国際情勢の大局を理解する上で、基本的にこのようなハンディがあると自覚すべきでしょう。そのためでしょうか、日本の外交全般の歴史をふりかえりますと、率直に申して、日本は外交が上手な国とはとてもいえませんし、中国との関係についても、友好2000年とは申しますが、しかし、決して上手にやってきたとはいえないでしょう。
2.尖閣問題
そこで、最初に、いわゆる尖閣問題についておはなしします。先ず、領有権についてです。
尖閣諸島は、沖縄諸島の西端の北側にはなれて位置しているので、沖縄についての説明からはじめなければなりません。
徳川時代の初期慶長14年、鹿児島の島津藩が琉球に攻めこみ、それ以降幕末まで搾取と支配をつづけていました。明治維新で島津藩の出身者が、明治政府の中枢を占めたので、日本は、島津藩の習いで、それまでの経緯があって、沖縄朝野の民意を全く無視して、当然のように琉球を日本の領土にしてしまったのです。それが明治13年のいわゆる「琉球処分」です。「処分」という言葉が示すような物扱いです。私は昭和2年の生まれで、戦争の終ったときは18で、戦前戦中の教育を受けた者です。日本の歴史、昔は国史といったのですが、国史の教科書のなかに琉球のことなどほとんど書いてなかった。国史の参考書のなかに、注釈に3~4行、琉球を日本の領土にし、沖縄県にしたという記述があったと記憶する程度です。それまで、曲がりなりにも独立していた「琉球王国」について教えられた記憶が全くありません。しかも、この「琉球処分」には尖閣諸島は含まれませんでした。そしてその状態が、日清戦争の前までつづきました。それは、当時の段階では、中国から領有権について異議が提起される惧れがあったため、尖閣を領土に編入することを差し控えたとみられています。
その後、わが国は、日清戦争(1894~1895)に際して、軍事的に優位にたったとの認識から、1895年1月14日、尖閣を沖縄県に編入しました。その時も公に発表すると、中国を刺激することを惧れて公表しませんでした。このような経緯からみて、日清戦争の時に日本が尖閣を領土にしたことは歴史的事実です。
その次に、第二次大戦中の昭和18年、1943年の11月に、アメリカのフランクリン・ルーズベルト大統領とイギリスのウインストン・チャーチル首相、中華民国の蒋介石大元帥の三首脳がエジプトのカイロで会議を開催し、連合国の日本に対する戦争目的及び戦後のアジアの国際秩序を想定する討議を行いました。そして「カイロ宣言」が発表されたのですが、その中にはっきり明文で、日本が中国から「窃取した」領土、「例えば東北四省、台湾、澎湖島等」は中華民国に返すべきである、と書いてあります。それがそのまま1945年7月、日本の降伏の前提になった、ポツダム宣言の第8条にうけつがれ、このポツダム宣言第8条は、ずっと後のちょうど40年前の1972年9月29日の国交正常化の時の日中共同声明の中にもうけつがれ、ポツダム宣言第8項は守る、遵守するとはっきり書かれています。これらの文書から判断しますと、「尖閣は、日本の固有の領土で、領有権の問題は存在しない」という日本政府の現在の主張は弱いといわざるをえないと思います。
もうひとつ。領有権についてこのような見解の不一致そのものよりも、より重要な問題があります。それは、見解が対立しているから、話し合いもしないという立場を日本政府がとっていることです。これは大変なことなのです。話し合いしないというのは、では、喧嘩するんですか、戦争に訴えようというのですか。これは大変なことだと思います。紛争や問題があれば、とにかく平和的手段により解決すべきことは、日中国交正常化の際の共同声明第6項及び平和友好条約の第1条2項の明文により約束されておるところです。
尖閣問題については、共同通信出身の岡田充(タカシ)さんという方が、『尖閣諸島問題』(蒼蒼社発行)という本を出版しておられます。非常によく書けています。この本の帯に、尖閣については、譲渡するか、棚上げするか、戦争するか三つしか解決方法がない。どれを選ぶか、と書いてあります。この指摘のとおりです。いずれにしても、両方の考え方が違うのですから、話し合いをするしかないと思います。
私が小学校5年生の時(1937年)にいわゆる「シナ事変」が始まったのです。盧溝橋事件です。私は新聞のあのときの見出しを覚えておりますが、当時の近衛首相が「蒋介石を相手にせず」という「近衛声明」を発表してしまいました。相手にせずということは交渉しないということです。軍隊を送って軍事行動を始めてしまって、何年やっても、アメリカのベトナム戦争よりもよっぽど悪い泥沼に引きずり込まれて、日本はああいうことになってしまったのです。両方の見解が違うのですから話し合いをしなければいけない。これは今日の世界で常識といってよいことです。この問題については、日本国内でいろいろの意見があります。係争があるのは事実だから、話し合いをすべきだと、政府と違う意見をいう人を、すぐ「国賊」とか、「非国民」とか、そんなことをいうようでは、私のような老人は、戦前戦中のあの暗い日本の国を思い出してしまいます。
3.沖縄とそこにある米軍基地
つぎに、沖縄と米軍基地の問題に入ります。なぜこの問題を考えたか。先程も申しましたが、沖縄については、尖閣についてのところで言及しましたが、日本の、徳川時代以来の政策ないし取扱いが、単純にいえば、差別と支配で、それがずーっと続いてきたという歴史があります。11月に沖縄に行きまして、知事を二期おやりになった大田昌秀先生をまた久しぶりでお尋ねして、その他2、3の有識者の方々に会ってお話しを聞きました。そして、私自身の沖縄に対する歴史認識があやまっており、現実の情勢認識も全く不正確なものだったと痛感いたしました。鳩山由紀夫元首相は、いまあまり評価されておられませんが、かつて首相として普天間基地は「最低でも県外移設」だといわれたことで、沖縄で非常に尊敬されています。その大きな効果は以後ずっと残っているのです。沖縄県民の気持ちをくみ取ってくれた、という評価です。この気持ちは元に戻らないと思います。
沖縄は、第二次大戦中唯一の地上戦の地域になって、沖縄に今生きている私位の年の人で、家族の人が殺されたり、死ななかった人がない位のそういう酷い目に遭った、そのうえにサンフランシスコ平和条約第3条で日本は沖縄を放り出してしまった。アメリカが信託統治するかもしれないから、それについては何ら異議を唱えないということで、小笠原、奄美といっしょに、日本はいわば放棄してしまったわけです。沖縄の人々はそれ以後、27年もアメリカの軍政下、占領下にあり、人権も守られない状況がつづきました。それで、沖縄の人々はアメリカの軍政下にとどまるよりは、民主主義と人権尊重の新憲法が施行されている日本の国へ戻ったほうが、よいと思って、「復帰運動」がおこり、「復帰」に反対する人もおりましたが、結局沖縄は「復帰」に同意したのです。昨年2012年で「復帰」後既に40年のいま、その結果はどうかというと、米軍の地位は変わらない、米兵の犯罪は頻発するが、住民は酷い目に遭っても占領下の取扱と変わらないという批判が沖縄の人には強い。ひとことでいえば、これ以上の人権侵害は許せないという感情です。とくに最近落ちることで有名なオスプレイなどを沖縄に持ってくることになり、沖縄の世論は非常に硬化しています。普天間の辺野古への移設も、超党派で反対していますので、実現の可能性はないと思います。安倍政権になっても、沖縄の基地反対の超党派の世論が軟化する可能性はないようです。
もうひとつ、沖縄で強く印象に残ったことは、大田元知事からいわれたことですが、東京から来る週刊誌の見出しを見ると、今にも日本と中国が戦争を始めそうだと書いてある、これは大変だ、といわれるのです。第二次大戦の時でも、とびぬけて酷い目に遭ったのは沖縄なのです。本土も東京も距離があるから平気な顔をしているが、ミサイルでも飛んできたら、いちばん先に酷い目にあうのは沖縄だ、第二次大戦の時に、本土の日本政府は、本州のたとえば九十九里浜に上陸するといわれた米軍の来攻を少しでも遅らせるために、沖縄を戦場にして、数か月の時間を稼ごうとした。そのために酷い目にあったのは沖縄だ。あの時の記憶がよみがえる。今度も同じようなことをやられるのではないか、そういう強い懸念があるとのことでした。
沖縄では、具体的な県民の経済生活を守る上で、何がまず念頭にあるかといえば、尖閣の周辺の漁業権の問題です。漁業ができればよい。あの辺りは台湾の漁民も操業にきています。ですから、沖縄の業界の人々は、現に台湾の東海岸の宜蘭の人々と漁業について話しあいをしているとのことです。付け加えますと、先程も「琉球王国」の話しを申し上げましたが、沖縄では、そもそも沖縄が日本の固有の領土と思っていないのです。明治13年までは、「琉球王国」という、弱いが曲がりなりにも立派な独立国だったのです。清国との間に外交関係を結び、使節が行ったり来たりした。江戸幕府にも使節を送っていました。現に当時「琉球王国」から日本に派遣された方の四代目か五代目の方が東京にいらっしゃいます。東京の沖縄県人会の名誉会長をしておられる川平朝清(カビラチョウセイ)先生です。
いま、沖縄の空気を全般的に判断しますと、もう、東京の政府も、国会も、永田町も、霞が関もあてにはできない。アメリカのいうことを差別的に沖縄に押し付けてくるだけだ。アジアの安全保障のため、日本の安全保障のために沖縄に基地を置かなければならない。そういうことばかりいわれつづけている。これは人権侵害だという意識が強いのです。これ以上東京に頼ってもあまり効果はないという気持ちです。現に(これは、西銘知事以来実行されてきたことですが)この間も仲井眞知事はワシントンへ行って、普天間のことで直接米側に申し入れしています。
特に行政改革の一環として、東京では道州制ということがかなり論議されていますが、九州と一緒にされる道州制には、沖縄の人々はこれまた超党派で絶対反対のようです。沖縄の立場は、九州と一緒にされてしまうなら、現状よりもっと悪くなってしまう。弱者切り捨てで沖縄がやられてしまう。これには、昔からの徳川以来の琉球が搾取されてきたという歴史の怨念がある。くりかえしになりますが、沖縄で何回もいわれたのは、1609年という年です。1600年は関ヶ原の戦争です。1603年徳川幕府は江戸に開いた。その6年後の1609年という早い時期に、島津藩は-徳川幕府が認めたかどうか知りませんが-軍隊を出し、沖縄に攻め込んだ。そのとき、どういう武力衝突があったか分かりませんが、沖縄は非武装の平和国家ですから、簡単に押さえられてしまった。しかし、その後も曲がりなりにも「独立王国」を続けていた。その間、奄美大島と同じように取扱い島津藩は沖縄にサトウキビを植えさせ、それで島津の財力はゆたかになった。そういう怨念、被差別観、圧迫感から道州制反対の世論が強いのです。
更に、私は知らなかったので、吃驚したことですが、「琉球大学」に事務局をおく「沖縄自治研究会」の活動です。既に1990年代から真剣に検討されているのはスコットランドの歴史です。スコットランドは独立王国だったけれども、1707年に英国により「連合王国」に組みこまれてしまった。「連合王国」という名前だが、実際はイングランドがスコットランドを支配してきた。ところが、少なくとも自治を回復しようとする市民運動が結実して、遂に1999年にスコットランド議会ができて、スコットランド内のことは、安全保障とか、通貨・金融以外の一般の内政上の事項はその議会限りで決められることになった。スコットランドは、更に明2014年には、独立の可否をきめる住民投票をおこなうことになっています。直ちにこれでスコットランドの独立が回復されるかはもちろんわかりませんが、このような経過について、沖縄の人は詳しく研究をつづけてきており、これを参考にして、既に2004年に、『沖縄州基本法試案』を作成しています。いまただちに独立しようとするのではありませんが、少なくとも、現在のスコットランドのような自治権をえたいという考え方は強いです。これは一部の知識層だけがやっておられることではありません。県会議長の喜納昌春(キナマサハル)氏が熱心です。政界で、超党派的にこういう動きを支持する動きがある。そして県商工界なども支持声援しているとのことでした。
更に複数の方々からきいたところでは、学生など沖縄の若い人たちの中では、日本の枠内の「自治」では不充分だ、現状を打破して独立しなければならないという強硬な意見もかなりでてきているとのことです。それもマハトマ・ガンジーのように非暴力でいこう。非暴力・非協力で独立を勝ち取ろうという考え方があるということを聞きました。これは大田先生もいっておられたことです。
独立論を展開しているいちばんいい本は『琉球独立への道―植民地主義に抗う琉球ナショナリズム』(法律文化社発行)です。著者の松島泰勝氏は京都の龍谷大学教授です。これは琉球独立の展望についてはっきりまとめて書いた最初の著作ではないかといわれていますので御紹介します。しかしこのような動きは、言葉の問題なのですが、厳密に言えば日本からの分離ではないのです。スコットランドと同じように、元々独立王国だったものが復元する、「琉球王国」の復元という言葉を使うべきだと思います。
よく沖縄で話を聞くのは、昔南洋で日本の委任統治領であったミクロネシアとか、サイパン島とか多くの島嶼がありますが、人口3万のところも独立しています。沖縄の人口は140万もあるわけですから、経済の自立さえできれば独立してもいいのではないか、当然独立すべきだ、こんな差別を受ける状態がつづいてはならないという主張です。また、特に沖縄で屡々きくのは、「自己決定権」という言葉です。これは英語のself-determinationの和訳です。普通は民族自決と訳されている言葉ですが、沖縄の人が「民族自決」という言葉を使わないのは、「集団自決」ということを連想するから「民族自決」を使わないのであって自己決定権というのだ、と聞きました。かつてはアメリカの基地への依存度がかなり高かったが、今はわずか5%です。沖縄の財政、経済は観光その他で自立できる可能性があり、米軍がいなければ食べていけないということは、基本的に既にないわけですから、これらのことを考えますと、沖縄は、そろそろ曲がり角に来ているのではなかろうかと思います。
ただ、最後に申し上げたいのは、沖縄・琉球の今後につきましては、あくまでも、ああしろこうしろと外部が干渉すべき問題ではない。『琉球独立への道』という本が出ている世論もあり、主として沖縄人自身がお決めになる問題であると思います。しかし、沖縄がスコットランドのように自治を求め、更には独立も視野に入れることとなる場合には、国際環境(あるいは国際世論)がそれを支援する、特に経済交流の促進によって経済的自立を支援することは必要です。国際環境ということになりますと、日本は、今までの経緯もあり、歴史問題もありますから、沖縄の独立回復を祝福して支援するということが当然あってもよいと思います。もう一つ、国際的支援ということから言えば、自然に考えられるのは、中国の支援です。中国(特に福建省とか台湾とか香港とか)は歴史的にも、また現在の交流関係の上でも非常に深い関係にあります。沖縄文化が基本的には福建文化だともいわれています。福建のお墓と琉球のお墓は同じような形をしています。また、沖縄では習近平氏が今度中国のトップになったことをとても喜んでいるとききました。どういうことかといいますと、習近平氏は福建の省長を随分長い間やっており、福建省長のとき、沖縄との地方交流を随分熱心に実施され、沖縄に理解があると認識しているとのことでした。
沖縄については、東京の政府の政策と現地の世論とのギャップが、既にどうにもならないほどひどくなっているといっても過言ではないしょうが、これには、東京の全国紙などマスメディアにも責任があるのではないでしょうか。
4.「日中戦略互恵」と「日米同盟」の矛盾
その次は、日本外交全般のことになるのですが、いわゆる「日中戦略互恵」という言葉があります。私見ですが、それと「日米同盟」とは基本的に矛盾していると思います。そこで、今日お配りした資料のひとつとして、首相、外相をつとめた外務省の大先輩、吉田茂よりまだ10年以上先輩の石井菊次郎元外相が昭和10年、1935年に書いた手記があります。その頃は、日本の軍部、特に陸軍がナチスドイツと軍事同盟を結ぶことに熱心だったときで、それに対する批判です。石井氏の主張は、日本の陸軍が一生懸命になって同盟関係を結ぼうとしているドイツにはビスマルクの伝統がある。ビスマルクは、「同盟」とは、強い国が弱い国を支配したり、利用したりするための手段であると公然と述べていた。だから、日本がヒットラードイツを利用できるならとも角、ヒットラーに利用されるのであれば、日独軍事同盟は作らないほうがよいと言ったのです。その頃こんなことは発表できませんでしたから、これを保存しておられた遺族が、戦後、鹿島平和研究所に提供され、公開されたものです。「日英同盟」は、一方が風上に立ち他方が其配下に置かれることがなく、紳士的に運営されたが、これは、珍しい例外的なケースであった。軍事同盟は一般論として、強国は弱国を支配し、利用するものだ。故に、ドイツと同盟するのはあぶない。よく考えないと利用されるだけだと主張しています。
私は日本とアメリカとの友好協力関係は大事だと思っています。私はアメリカに留学しておりましたし、両親も関東大震災の前に米国生活を経験しましたし、母はアメリカに留学していましたから、家族ぐるみでアメリカという国は好きですが、日本とアメリカとの関係は独立国同士の関係でなければならないと思っています。私が、18歳、旧制高校2年の時に日本が敗けて占領軍が来たのですが、当時の日本では米占領軍がいつまでもいるという認識は全くありませんでした。占領軍総司令官マッカーサーも、占領目的は日本の民主化のためだと考えていたので、いつまでもいるなんて考えもしなかった。ところがその後の冷戦の惰性でもう68年も駐留がつづいているわけです。
今若い方は生まれたときから米軍はいるわけですから、アメリカ軍がいるということは空気か水みたいなもので分からない。しかし他の国から見ると、また、昔のわれわれのような老人の常識からすると、軍隊は戦争するためのもので、端的にいえば超法規的なものなのです。何でもできる組織です。それが、自分の国の軍隊ならとも角、他の国の軍隊が、半恒久的に、しかも日本の首都圏にもいるのは、何とも異常なことです。これでは、日本が半分しか独立していないと外国人にいわれても仕方がない。
エズラ・ボーゲルというハーバード大学で日本や中国を研究している学者が、安保のことで、日本は米国とは対等ではないとはっきりインタビューで述べています。また、スタンレー・ホフマンというハーバード大学の安全保障の専門家が、随分前に日米安保はアメリカが日本を管理するための手段だとインタビューで述べて、朝日新聞が報じたことがあります。われわれは、経済大国だと自称していますが、アメリカとの関係は、端的にいうと上下関係です。非常に残念だけれど、端的にいえばそういうことだと観念せざるをえません。「日米友好協力」といっていればよかったのですが、いつの間にか「同盟」という言葉を定着させてしまったことは遺憾です。これは、一部の人たちが、「同盟」を強調すれば強調するほど、日本の世界政治での地位が高くなるだろうと勘ちがいしたことによるものですが、しかし現在の日本の地位はむしろどんどん下がってきているというのが、歴史の現実です。
私は1971年から73年まで当時のいわゆる東ヨーロッパ「ソ連圏」のチェコスロバキアに在勤していました。あの国は、ルーマニア、ブルガリア、ハンガリー、東ドイツと同じように「ソ連圏」の中にくみこまれていて、重要な問題ではすべてソ連の指導に服していました。しかしチェコスロバキアを含むそれらの国ですら、ソ連との関係を「外交の基軸」と公式に述べたことはなかったのです。特定の二国間を「外交の基軸」といっている国は、おそらく現在の世界でも日本だけではないでしょうか。「外交の基軸」をそう定めてしまえば、中国の関係にしても、他の国との関係にしても、「日米同盟」の枠内でしか考えられないわけです。日中間の「戦略互恵」の関係は、そのような限界の中でしか思考できないことになります。
中国は、1978年に鄧小平氏の指導で改革開放政策に舵をきり、周辺に平和の環境を作ることを政策としてきました。そうなると米軍がアジアにいる必要が低下してくるわけです。それが困るものだから、米国は所謂「不安定要因」を殊更に強調し、台湾海峡に航空母艦を持ってきたりして、橋本竜太郎首相のとき、1996年に日米安保共同宣言を発表しました。あれは日米安保を自然死させないで延命させる仕かけだったと考えられます。アメリカの国益からしますと、日本を押さえるのと、中国を押さえるのとふたつの使命を担っている日米安保を存続させる必要があると判断したのでしょう。そういう状況が現在に至ってもまだ基本的にはつづいています。しかしこれについては、そろそろ曲がり角にきています。この地上のものはわれわれの人生と同じように、すべて始めがあれば終わりがある。「日英同盟」にしても20年しか続かなかったのです。「日米同盟」もいつまでもつづくとは限りません。米国の政策も、財政上の制約から、「内むき」になりつつあるようにみうけられます。「人間万事塞翁が馬」で、もしかすると、沖縄の情況や尖閣問題が何らかの契機になるかも知れません。
5.後藤田正晴、加藤周一両氏の遺訓
最後に、後藤田正晴さんと加藤周一さんの両先生の遺された言葉についてお話しすることにして、資料をお配りしたのは、これら両先生が、今日の日本でわれわれが念頭におくべき「国の在り方」―「国の在り方」において、内政と外交が表裏一体のものです―について、まことに重要な教訓を遺されたからであります。
後藤田さんは、日中友好会館会長で、週に1回来ておられ、おはなしを聞いたのですが、日本には、既に仮想敵国はない、況んやアメリカと共通の仮想敵国はないのだから、日米安保条約を終了させ、平和友好条約に切り替えるべきだと何度も何度も公式の場で発言されました。日本は独立して自立する、頭の中を自立する、自分でよく考える、陸軍主計大尉として従軍された戦争中の経験がありますから、絶対に戦争してはいかん、民主主義でやらなければいかん、そういうことを言っておられたその一例がお配りした資料です。
もうひとつは、加藤周一先生の言葉です。加藤先生にはお元気なころ二か月に一回位お話しを伺っていました。加藤先生のこの文章は、日本は二つの過ちを犯した。一つは、明治の初めから自分の利益だけを追求して、植民地支配をしたり、侵略戦争をしたりして、中韓両国民を酷い目に遭わせた。それは大きな失敗だった。二つ目の失敗は、その失敗についての反省をしないで、「冷たい戦争」にも便乗し、経済的利益を追求して、次の50年を過ごしてしまった。二つの過ちをよく考えて、はじめて、日本の将来の展望はひらける。加藤先生は、歴史の反省を充分にしなければ、日本の将来は明るくないといっているわけです。
後藤田先生もいつもこれから日本はどうなるかと、とても心配しておられました。私に、「君、ときどき本屋に行って新刊書を見るかね」といわれました。見ないといったら「ときどき本屋に行って、並んでいるいろいろな新刊書を見なけりゃだめだよ。新刊書や週刊誌の見出しをみると、昭和の初年の頃のような雰囲気が出ている。これでは危ないよ。」といっておられました。
加藤周一先生も同じように、最近の世相をみると、戦前戦中とかわらない空気を感ずるといっておられました。加藤先生と後藤田先生は、岩波の『世界』2005年8月号で対談が掲載されたことがあるのですが、その中で憲法は日本の安全のみならず、周りの国の安全のためにも大事だ。日本は憲法の特にその九条は変えないほうがよい、との主旨で意見一致していました。日本が反省し、中国や韓国を再び脅かさないのであれば、アジアは静かになるということです。
結局、後藤田先生と加藤先生の言葉を、短く言えば、憲法を守っているか、憲法が定着しているかどうか、平和主義と民主主義が定着しているかどうかということです。おふたりが心配していたことが、杞憂ではなくて、現実になりつつあるのではないでしょうか。
登場した安倍政権は、歴史認識をはっきりと表明した「村山談話」や、従軍慰安婦問題での反省を述べた「河野談話」の双方の「見直し」を行うとし、更に、国際社会の普遍的な倫理・価値観を掲げている憲法について、戦勝国に「押しつけられたもの」だから、改正を検討すると明言しています。そして、「価値観外交」を推進するといっていますが、如何なる「価値」を追究しようとしているのか、理解に苦しみます。自ら国際的孤立を選んでいるようにさえみえます。
更に注目すべきものとしては、石原慎太郎前都知事の考え方があります。石原さんは、この間新聞に出ましたが、ワシントンへ行って、ヘリテージという団体で講演しました。それについての日本の新聞報道によれば、尖閣は日本政府がしっかりしないから、東京都が買って守りますとの趣旨でした。これがいわゆる尖閣問題のゴタゴタの始まりですが、この演説では、尖閣を東京都が買いますということは、終わりの三分の一位に出てくるだけです。その前に、長々といろいろな石原さんの世界観が出ている。その中には、特に、イスラエルは核武装した。核武装しているから一人前でものがいえる。日本もそういう国になって、そういう国としてアメリカに認めてもらうのがよい。こういう趣旨を述べたくだりがあります。その部分は日本で報道されませんでした。
結局、石原さんは、イスラエルのように核武装して、アジア大陸にむかって睨みを利かす、そういう日本を考えていることは間違いないようです。アジアのなかで孤立すれば、世界で孤立することは日本が第二次大戦でえた歴史の教訓ですが、そういうことは、石原さんの念頭にないらしく、米国へ行って、日本も核武装して当然というようなことをたくさんの人の前で公然といっているわけで、非常に危険だと思います。
私が小学生の頃、日本は世界の一等国だと散々教えられました。海軍の強いのは、イギリスとアメリカと日本だ、世界三大強国の一つだといわれたことをはっきりおぼえています。しかし、21世紀の日本は、もうそういうことは考えないで、中位の特色のある国であればよいと思います。これからどんどん人口も減っていきます。現に60歳以上の人が三分の一という老人国でもあります。あまり派手なことを考えないで、地味に、足を地につけて、環境問題その他で貢献できることがあれば貢献するということで国際社会の中でやっていくということしかないのではないかと思います。
最近、朝日新聞で、アメリカのジョン・ダワー(敗北を抱きしめて』という書物を書いた人)ともう一人、ドナルド・ドーアというイギリスの学者、この二人がインタビューで日本は思考を独立させなさい、独立していないと、アメリカがどこかで始めるかもしれない戦争に巻き込まれてしまう、と述べています。同感です。
これから日本の民主主義が定着するかどうかについてですが、私は、日本に民主主義が定着しにくい理由があるとすれば、そのひとつは、国の政治のやり方が、かつての天皇制のなかで官僚がやっていたこと、官僚が全て物事を処理してゆく、一般の国民には、「知らしむべからず由らしむべし」、ただ政府に依存させておけばよいのだ、というやり方が未だ残存していることではないか。民主主義ではなくて、官治主義が残っているためではないかと思います。
もうひとつ。インドで3年間在勤して気がついたことです。インドでは、一人一人がそれぞれの考えを持っていることをむしろ当然と認め合っています。AさんとBさんがお互いに自分と違う考えを持っているのは当たり前だから、お互い二人が口角泡を飛ばしてワーワーやっているのを聞いていますと、いうだけいって、意見が違うことが分かるとサッパリしてサヨナラです。別に喧嘩するわけではなく、しこりが残るなどということは絶対にありません。国内で、インド人たち同士の間でそうですし、インド人は外国に対してもいいたいことを120%主張しますから、アメリカなんかは、こんな煮ても焼いても食えない国はないと思っているようですが、インドが何考えているか誤解される心配はまずないのです。いいたいことをいって、違う意見は違う意見として、話し合うということでやっているのがインドです。
ですから、インドは中国との間の国境問題は合意していない。もう半世紀以上合意していないです。だけど、そのことで戦争するわけではない。ときに話し合っては、両方の意見が違う、立場が違うことを確認してサヨナラなんです。そして、経済交流など共通利益をはかることで、外交関係をつづけてきています。インドも中国も大国だといっていいと思います。故丸山真男教授もまた同じようなことをいっています。日本では、多様性を認めず、意見は必ず一致せねばならないと考える傾向が強い。違う意見を互いに許さないという伝統がある。これでは、民主主義は育ちにくいということをいっています。結局、われわれ日本人は、物事を合理的に検討し議論するということに不得手なのです。何となく雰囲気で物事が決まる。何となく思考停止で、挙国一致の雰囲気で物事が動く。日本ではそういう傾向があることを否定できません。まことに「民主主義」は難しいことだと思います。
更にもうひとつ。武田清子先生が非常に立派な文章を書かれております。武田先生が1957年、日本が国連に加入した昭和32年に、信濃毎日新聞という立派なローカル新聞に寄稿された文章です。それは、日本の明治以来の外交の流れをみると、地位を求める虚栄心がある。虚栄心は捨てよう。そんなことは考えずに、また、どこかの国―どこかの国と書いてあります―にぶら下がってうまいことをやろうなどと考えるべきでない。短期的には不利になっても自主独立の気概をもっている多くのアジアアフリカの新興国といっしょになってやるほうがよい。どこかの国にぶら下がって世界の一流国になろうとか、何等国になろうとか、何番目だとかいうことは考えない方がいい。と武田先生は書いておられます。これは至言です。そのように考えて謙虚にやっていけば、これだけ教育水準が高くて、科学技術もあるのですから、それなりに、日本は、国際社会、特に中国との友好協力と相互信頼の関係を築くことができるでしょう。限界を弁えて、足元を見ながら現実を直視して外交もやっていけば、日本も存立をつづけていけるだろうと思っています。ご清聴ありがとうございました
(2013.1.19 日中学院にて)